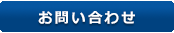カーボンニュートラル社会実現に向けた川崎重工グループの取り組み

企画本部 サステナビリティ推進部 環境企画課
山本 敏之 氏
初めにカーボンニュートラルに関する世界の動きについて解説します。2015年に採択されたパリ協定では地球温暖化対策として2100年の世界の平均気温を産業革命前と比べ1.5℃程度の上昇に抑えることを目標に定めており、2050年にカーボンニュートラルが実現すればそれが可能といわれています。しかし、日本でも2050年までの達成を目指しているものの、温室効果ガス濃度は観測史上最高を更新中で厳しい状況にあります。
次に、カーボンニュートラルに向けた具体的な取り組みを紹介します。世界では石炭火力を廃止しメガソーラーや風力発電などへの移行が進んでいるといいます。また、EUでは企業や組織に対して排出するCO₂に応じた金銭的負担を課し、削減できない分は金銭で売買できる制度や、輸入品に国内と国外の炭素価格の差額の支払いを求める制度もできています。さらに、世界の大手企業では、自社だけでなく取り引きのあるパートナー企業を含めたサプライチェーン全体でCO₂削減に取り組む動きも出てきており、米国のApple社は、部材の発注先の企業にも再生可能エネルギーへの変更を要請しています。今後は日本でもこのような動きが広がると思われます。
続いて、川崎重工グループの取り組みについて紹介します。日本では現在、エネルギー自給率が13%しかない上、使用するエネルギーの83%が化石燃料であることを踏まえ、同社では2030年までに国内全事業所において、水素発電を軸にCO₂の発生をゼロにする"自立的なカーボンニュートラル"の実現を目指すことを明示しています。具体的には、年間約30万t発生しているCO₂を減らすため水素発電や再生エネルギーへの切り替え、長年蓄積してきた潜水艦内でのCO₂除去技術を駆使して大気や排ガスからCO₂を回収するなど、省エネ化を進めています。2030年以降は、海外の拠点や海外での資材調達においてもその方針を適用していく予定です。
さらに、同社が描く水素発電の普及に向けたプランですが、まずは、水素をオーストラリアでコストを抑えて製造・液化し、船で日本に運び国内に供給する仕組みについてです。これらは水素ガスタービンを用いた発電と、水素エンジンモーターサイクルをはじめとするモビリティへの転用が想定されています。現在、国内での普及量はそれほど多くありませんが、2030年には年間300万t、2050年には年間2,000万tの水素の供給が想定されます。一番の課題はコストで、現在年間で36tを運ぶのに約170円/N㎥と、LNGガスの10倍近くかかっていることから、2030年には水素単価を約30円/N㎥まで下げることを目標に掲げています。同時にカーボンニュートラルにはサプライチェーン全体で進めることが欠かせません。製造事業者は使用する素材を現状より少ないエネルギーで加工できるものに代えたり、輸送事業者は梱包を簡素化してエネルギー使用量を抑えたりと、多様な対策が考えられます。まずは自社のCO₂排出量を算定し、削減量を見据えた上で何ができるか検討してみてください。川崎重工グループでは、本年度から主要な取引企業を対象にカーボンニュートラルの勉強会や交流会を開催しています。
最後に、国の「CO₂削減比例型中小企業向け支援事業」やカーボンニュートラルを進めるための相談窓口もうまく活用しながら、ぜひ前向きにカーボンニュートラル社会に向けて各企業も取り組んでもらえたらと思います。